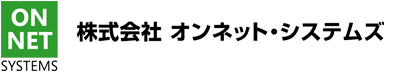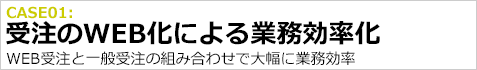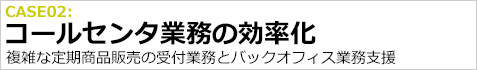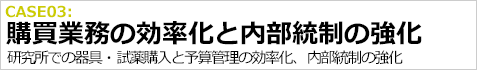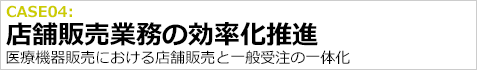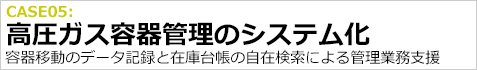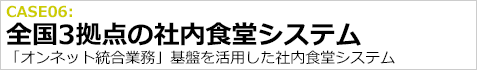-
「考え方」とは、当社が「販売、購買などの基幹システムをどう見ているか」という点と「その見方に対するシステム構築方法論」です。「考え方」はオンネット統合業務システム商品・サービス開発の前提になっています。
-
オンネット統合業務の機能は広範に及んでいます。またその機能は日々拡大しています。販売、購買はほぼ網羅された実感はあります。在庫管理、生産管理は販売、購買機能との連携以外にも利用先ごとに新たな機能や要件がありそうです。最近の拡張はインボイス制度、電子帳簿保存法への対応、また基幹データとモバイル端末連携への対応など基幹データを社外利用(取引先、外出先など)などに広がっている感があります。現在保持している広範な機能をご確認ください。
-
基幹システムは会社ごとに要求仕様が異なります。システム運用を通じて新たな機能追加や変更などが必ずあります。業務手順、管理手順が長年同じという事はありません。オンネット統合業務は開発方法を統一して変化に備えています。しかし開発方法も技術の変遷があります。ただ業務を定義するDB項目、DB構造は変化がありません。業務を表現しているDB構造を中心に、カスタマイズが柔軟に出来る仕組みをオンネット開発基盤としています。「カスタマイズとオンネット開発基盤について」として説明します。
-
1995年頃まで高額な大型汎用コンピュータ(メインフレーム)が中心に使われてきました。企業には情報システム部という組織があり専門家が配置されていました。2000年頃からPCの能力が向上しメインフレームの衰退が始まります。クラウド利用も進みました。「システムはRPA、Aiで簡単に出来る。DXだ!」という考え方も出てきました。そんな中、当社の考え方は「PC・ネットワークコストは劇的に下がった、がしかし、システム構築手順に劇的変化は無い」です。重要な事は、自社の業務(機能と情報)を文書に定義することと考えています。システムは、導入企業の業務管理能力(文書定義)を超えられないのです。
-
オンネット統合業務は標準機能に備わっていれば、原則的には一時費用は発生しません(データセットアップ、インストール費用は発生します)。ただし維持利用料金が月額として発生します。カスタマイズが必要と考えますので、その部分は初期費用として発生し、年間保守額(月額分割)が発生します。
-
基幹業務利用者は社員、受入れ出向や派遣が主でしたが、①利用場所の観点や②利用者属性の観点で考える必要性が出てきました。利用局面(移動中、自宅、取引先など)が拡大したためです。「働き方改革」「コロナ禍」でその流れは加速しました。ここでは「オンネット統合業務」の①、②の対応について書いていますが、昨今のゼロトラスト対応機運と重ります。「決して信頼せず、必ず確認せよ(Verify and Never Trust)」という考え方が重要と考え、その流れに沿うマスタ統合、認証・認可、利用デバイス対応を整備しています。